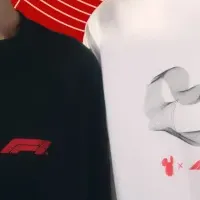

回転寿司で広がれ!鮭の日を祝うサーモン寿司の魅力とその歴史
食欲の秋に楽しむ「鮭の日」とサーモン寿司の魅力
毎年11月11日は「鮭の日」とされ、食欲の秋が深まるこの時期には、数々の旬の食材が人々の食卓を彩ります。今年はサーモン寿司の誕生から40周年を迎え、特にその魅力が広がり続けています。回転寿司店で人気のネタとして数々のメニューを彩るサーモンについて、その魅力や背景を探求してみましょう。
「鮭の日」の由来とは?
「鮭の日」は、一般社団法人日本記念日協会に認定された記念日の一つ。11月11日という数字が「鮭」とも言える形で構成されていることが、その由来です。その日に食材や魚介の情報を知り、味わうことで、消費者はこの日を楽しむことができます。
サーモン、回転寿司のスーパースター
回転寿司業界では、サーモンが不動の人気を誇ります。消費者調査の結果、14年連続で人気第一位を獲得する役割を果たしており、まさに回転寿司のスターと言える存在です。サーモン寿司が広まったのは1980年代、ノルウェーからの輸入によるもので、その後、日本独自の食文化にも定着しています。
養殖サーモン市場の成長
近年、日本国内の大部分のサーモンは養殖によって育てられ、その多くが安定した供給を実現しています。特に、養殖サーモンは寄生虫を含まないため、安全に生食可能で、多様な料理にも使われることから、人気が高まっています。日本のサーモン消費量はノルウェーなどからの輸入が85%を占めていますが、国内の養殖業者も増えつつあります。特に三陸や瀬戸内海、九州等では「海面養殖」が配信され、新たな特産品を生み出しています。
新しい技術で未来の養殖業
海面での養殖の他、革新的な陸上養殖の動きもあります。これは温暖化の影響で天然鮭が減少する中、養殖する魚達が快適に過ごせる環境を人工的に作るプロジェクトです。閉鎖循環式陸上養殖は、養殖場を海に依存せずに設立でき、水資源の節約や環境負荷最小化に寄与すると期待されています。この技術により、地域に新たな雇用をもたらし、食料供給の安定化が進むことが望まれています。
地域特産のご当地サーモン
日本各地では、それぞれ独自の風土や特性を活かした「ご当地サーモン」が育てられています。青森県の「海峡サーモン」や、兵庫県の「神戸元気サーモン」、栃木県の「うつのみやストロベリーサーモン」など、果物を合わせた新しい味わいを楽しむことができ、地域ブランドとしての価値も高まっています。さらに、愛媛県産の「みかんサーモン」や福井県の「ふくいサーモン」などが注目され、地域の産品としても魅力的でした。
ノルウェーサーモンの魅力
今年は日本とノルウェーの外交関係樹立120周年、そして海洋産業の発展を促進したノルウェーサーモンが日本に上陸して40周年という特別な年です。ノルウェーの清らかな海で育てられたサーモンは、日本の食文化に根付いた美味しさを誇り、その人気の秘密をノルウェー大使館の水産参事官、ヨハン・クアルハイム氏も語っています。
終わりに
今後もサーモンの魅力は広がっていくことでしょう。日本の養殖サーモンは地域特化型の新しい可能性を秘めており、サーモンを介して食文化の発展が進むことが期待されます。食欲の秋、ぜひサーモン寿司を楽しみながら、その魅力を再認識してみてください。










トピックス(グルメ)
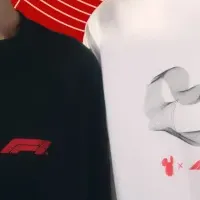




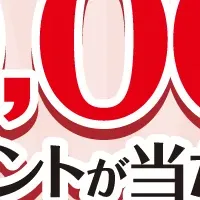


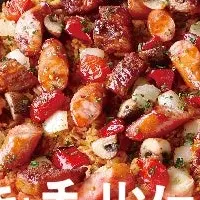
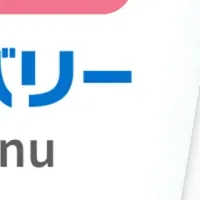
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。