

東北大学が水素利用拡大の研究開発プロジェクトを開始
東北大学の新たな挑戦水素利用の拡大に向けて
2025年度を見据え、東北大学がNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の研究開発事業に採択されました。今回のプロジェクトは、水素の普及促進を目指すもので、特に燃料電池や水電解技術の革新を目指しています。
事業の目的
本プロジェクトは、水素の製造と利用を効率化し、日本の産業競争力を強化することを目指しています。具体的には、水電解装置と燃料電池の高性能化や耐久性向上、コスト削減を図ることが重要です。そのためには、デジタル技術(DX)を活用した新たな共通基盤の構築が不可欠です。この基盤を通じて、国内外の競争力を強化し、水素社会の実現に寄与することを意図しています。
採択された研究開発内容
本プロジェクトは、3DCと東北大学の共同研究によって推進されます。特に、Graphene MesoSponge®(GMS)を基盤技術とし、次世代燃料電池や水電解に関連する要素技術の開発が進められます。この研究では、3次元メソポーラスグラフェンを用いた電極触媒の性能向上が鍵となります。
炭素材料は燃料電池の触媒金属の担体として重要ですが、耐久性を高めつつコストを低減することが求められます。例えば、動作温度の向上や、触媒金属の使用量を減らすことが挙げられます。GMSの独自の構造と特性を活用し、高い触媒活性と耐久性を持つ炭素材料を開発する予定です。
3DCの役割と目標
3DCは2022年に設立された東北大学発のベンチャー企業です。そのミッションは「化学と物理の力で世界に幸福を」であり、次世代炭素材料の量産化に向けた取り組みを行っています。特にGMSは、電池用途において注目されており、リチウムイオン電池、全固体電池、リチウム硫黄電池など、様々な分野での応用が期待されています。当社は、2024年にGMSをリチウムイオン電池向けに初めて出荷する予定で、多くの電池メーカーと協力し、技術の実証と商用化を進めています。
GMSの特長とその影響
GMSとは、炭素の厚さが原子1層分であり、スポンジのような三次元構造を持つ材料です。この特性により、柔軟性、多孔性、導電性、耐食性を兼ね備えた優れた素材として評価されています。これにより、電池の性能向上に寄与しながら、環境への負担を軽減することができるでしょう。また、GMSの技術革新は、カーボンニュートラル社会の実現にも貢献することが期待されています。
採用情報
3DCでは、様々な職種において新しい仲間を募集しています。勤務地は、仙台市、川崎市、岐阜県土岐市に展開しており、特に電池応用研究、製造シフトリーダー、材料応用開発、技術営業、経営企画など多岐にわたる分野での募集があります。興味のある方は、ぜひお問い合わせください。
まとめ
今回のプロジェクトは、日本の水素利用の拡大にとって画期的な一歩です。2030年のカーボンニュートラル目標達成に向けて、東北大学と3DCが共に新しい技術を生み出し、持続可能な未来を目指す姿勢は多くの人々に勇気と希望を与えています。これからの展開に注目です。

トピックス(その他)






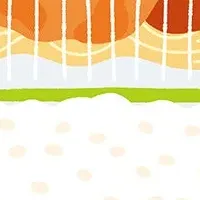



【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。